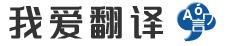- 文本
- 历史
大気中に含まれうる水蒸気量は「飽和水蒸気量」と呼ばれ、気温によって決ま
大気中に含まれうる水蒸気量は「飽和水蒸気量」と呼ばれ、気温によって決まっています。気温が高いほど飽和水蒸気量は大きくなります。飽和水蒸気量以上の水蒸気が大気中に存在すると基本的には凝結が起こりますので、それ以上の水蒸気は存在できません。飽和水蒸気量に対する大気中の水蒸気量の割合が、「相対湿度」です(温湿度計で表示される「湿度」と同じです)。現実の大気中では、あるところでは水蒸気が飽和し(雲が形成され)、あるところでは乾燥しており、平均的な相対湿度は5割程度になっています。地球上に含まれうる水蒸気量の大きさを巨大なプールに例えると、そのプールには5割程度の深さまで水(水蒸気)がたまっていることになります。ここで、プールそのものの深さは、気温、すなわち飽和水蒸気量で決まっています。ではCO2の増加による気温上昇によって、大気中の水蒸気量はどのように変化するのでしょうか。気候モデルを用いた予測によると、気温上昇によっても相対湿度はあまり変わらない、という結果が得られています。つまり気温上昇によってプールのそのものの深さは増える(飽和水蒸気量が増える)のですが、不思議なことに、同時に、気温上昇前と同じく5割程度の深さまで水が供給されるため、プールにたまる水の量(水蒸気量)も増える、ということです。このような水蒸気量の増加は、気温上昇によって海面からの水蒸気蒸発量が増えることで定性的には説明できます。しかし、「相対湿度がほぼ一定」となる理由は、必ずしも自明ではありません。しかしながら過去20年ほどの人工衛星による観測データによれば、気温上昇とともに水蒸気量の増加が観測され、気候モデルの予測する「相対湿度がほぼ一定」を支持する結果になっています(IPCC第5次評価報告書)。現段階ではデータ取得期間の短さやデータ品質の問題などもあるので、精度の高い観測が今後さらに増えていくと、より確かなことがわかってくるでしょう。。
0/5000
大气中可含有的水蒸气量称为“饱和水蒸气量”,由温度决定。温度越高,饱和水蒸气的量越大。如果大气中存在超过饱和水蒸气量,则基本上会发生冷凝,因此不会有更多的水蒸气存在。大气中的水蒸气量与饱和水蒸气量之比为“相对湿度”(与温湿度计上显示的“湿度”相同)。在实际大气中,水汽有的地方饱和(形成云),有的地方干燥,平均相对湿度在50%左右。如果把地球上所能容纳的水蒸气量比作一个巨大的水池,那意味着水(水蒸气)在那个水池中积聚了大约50%的深度。这里,水池本身的深度是由温度决定的,也就是饱和水蒸气的量。<br><br>那么大气中的水蒸气量是如何随着二氧化碳的增加而升高的呢?根据使用气候模型的预测,即使温度升高,相对湿度也不会发生太大变化。换句话说,水池本身的深度随着温度的升高而增加(饱和水蒸气量增加),但奇怪的是,同时,水被供应到了大约50%的深度,这和以前一样温度上升,所以水池里充满了水。这意味着积水量(水蒸气量)也增加了。<br><br>这种水蒸气的增加可以定性地解释为随着温度升高从海面蒸发的水蒸气增加。然而,“相对湿度几乎恒定”的原因并不总是显而易见的。但根据人造卫星近20年的观测数据,观测到水汽量随温度升高而增加,支持气候模型(IPCC)预测的“相对湿度几乎恒定”。第五次评估)下一次评估报告)。现阶段存在数据采集周期短、数据质量低等问题,未来随着更准确的观测结果会越来越清晰。<br>..
正在翻译中..
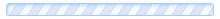
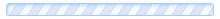
大气中含有的水蒸气量被称为“饱和水蒸气量”,是根据气温而决定的。气温越高饱和水蒸气量越大。如果大气中存在饱和水蒸气量以上的水蒸气的话,基本上会发生凝结,所以不能存在更多的水蒸气。大气中水蒸气量相对于饱和水蒸气量的比例是“相对湿度”(与用温湿度计表示的“湿度”相同)。在现实的大气中,有的地方水蒸气饱和(形成云),有的地方干燥,平均的相对湿度是5成左右。如果把地球上包含的水蒸气量的大小比喻成巨大的游泳池的话,那个游泳池里会有5成左右深的水(水蒸气)。这里,游泳池本身的深度是由气温,也就是饱和水蒸气量决定的。<br>那么随着CO2的增加,气温上升,大气中的水蒸气量会发生怎样的变化呢。根据气候模型的预测,根据气温上升相对湿度也不会太大变化。也就是说,随着气温的上升,游泳池本身的深度会增加(饱和水蒸气量增加),但是不可思议的是,同时,因为和气温上升前一样,以5成左右的深度供给水,所以储存在游泳池里的水的量(水蒸气量)也会增加。<br>这样的水蒸气量的增加,根据气温上升从海面的水蒸气蒸发量增加,可以定性地说明。但是,“相对湿度大致稳定”的理由并不一定明确。但是根据过去20年左右的人造卫星的观测数据,随着气温上升,水蒸气量的增加被观测到,成为支持气候模型预测的“相对湿度大致一定”的结果(IPCC第5次评价报告书)。现阶段也存在数据取得期间短和数据质量问题等,今后精度高的观测会更加增加的话,就更确切了。<br>。<br>
正在翻译中..
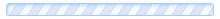
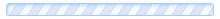
大气中含有的水蒸气量被称为“饱和水蒸气量”,由气温决定。 气温越高,饱和水汽量越大。 如果大气中存在饱和水蒸气量以上的水蒸气,基本上会发生凝结,所以不能存在更多的水蒸气。 大气中水蒸气量与饱和水蒸气量的比例为“相对湿度”(与温湿度计显示的“湿度”相同)。 在现实的大气中,有些地方水蒸气饱和(形成云),有些地方干燥,平均相对湿度只有五成左右。 如果将地球上含有的水蒸气量的大小比喻为巨大的游泳池的话,那个游泳池里就会蓄积水(水蒸气),达到5成左右的深度。 在这里,游泳池本身的深度由气温,也就是饱和水蒸气量决定。那么,随着CO2的增加导致气温上升,大气中的水蒸气量会发生怎样的变化呢? 根据使用气候模型的预测,得到的结果是相对湿度不会随着气温的上升而发生太大变化。 也就是说,由于气温上升,游泳池本身的深度会增加(饱和水蒸气量增加),但不可思议的是,与气温上升前一样,水会被供给到5成左右的深度,因此泳池中积存的水的量(水蒸气量)也会增加。这样的水蒸气量的增加,可以通过气温上升导致海面的水蒸气蒸发量增加来定性地说明。 但是,“相对湿度基本恒定”的理由并不一定自明。 但是,根据过去20年左右的人造卫星观测数据,观测到随着气温上升水蒸气量的增加,支持了气候模式预测的“相对湿度基本固定”( IPCC第5次评价报告书)。 由于现阶段还存在数据获取期短和数据质量的问题等,今后如果精度高的观测进一步增加,就会明白更加准确的事情了吧。。
正在翻译中..
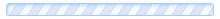
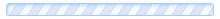
其它语言
本翻译工具支持: 世界语, 丹麦语, 乌克兰语, 乌兹别克语, 乌尔都语, 亚美尼亚语, 伊博语, 俄语, 保加利亚语, 信德语, 修纳语, 僧伽罗语, 克林贡语, 克罗地亚语, 冰岛语, 加利西亚语, 加泰罗尼亚语, 匈牙利语, 南非祖鲁语, 南非科萨语, 卡纳达语, 卢旺达语, 卢森堡语, 印地语, 印尼巽他语, 印尼爪哇语, 印尼语, 古吉拉特语, 吉尔吉斯语, 哈萨克语, 土库曼语, 土耳其语, 塔吉克语, 塞尔维亚语, 塞索托语, 夏威夷语, 奥利亚语, 威尔士语, 孟加拉语, 宿务语, 尼泊尔语, 巴斯克语, 布尔语(南非荷兰语), 希伯来语, 希腊语, 库尔德语, 弗里西语, 德语, 意大利语, 意第绪语, 拉丁语, 拉脱维亚语, 挪威语, 捷克语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 斯瓦希里语, 旁遮普语, 日语, 普什图语, 格鲁吉亚语, 毛利语, 法语, 波兰语, 波斯尼亚语, 波斯语, 泰卢固语, 泰米尔语, 泰语, 海地克里奥尔语, 爱尔兰语, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 白俄罗斯语, 科西嘉语, 立陶宛语, 简体中文, 索马里语, 繁体中文, 约鲁巴语, 维吾尔语, 缅甸语, 罗马尼亚语, 老挝语, 自动识别, 芬兰语, 苏格兰盖尔语, 苗语, 英语, 荷兰语, 菲律宾语, 萨摩亚语, 葡萄牙语, 蒙古语, 西班牙语, 豪萨语, 越南语, 阿塞拜疆语, 阿姆哈拉语, 阿尔巴尼亚语, 阿拉伯语, 鞑靼语, 韩语, 马其顿语, 马尔加什语, 马拉地语, 马拉雅拉姆语, 马来语, 马耳他语, 高棉语, 齐切瓦语, 等语言的翻译.
- sacrifice
- ᠹᠳ
- 进口的,一个月到货
- 我爱你
- VA
- 你好
- 您好,实在不好意思哟,您可以先签收一件商品,再申请退货一件哟~
- Như vậy, đội tuyển Mỹ một lần nữa "lỡ hẹ
- 明天寄出
- Now, I ‘ m iClass Twe, and Lou Yun is Cl
- 晚上好很抱歉您检查之前的表格了吗?是否有问题您什么时候方便支付剩余的款项呢月底我
- Theo các nhà khoa học, đến nay chưa có b
- 我妈妈有两个兄弟姐妹,是我舅舅和我小姨。我舅舅有两个儿子和一个女儿,我小姨有两个
- Festival
- sis
- 节日
- 对演练工作进行再次细化,确保能够演为战
- Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế
- 内蒙古
- Kl xboleh yer dtg kedai
- Verify the functionality of Wi-Fi connec
- 旅游,是生活中最大乐事。旅游虽然要花去不少钱,但它给人们带来的欢乐无穷无尽。一次
- 隂性生検に從つてマーキングを行う
- 涂